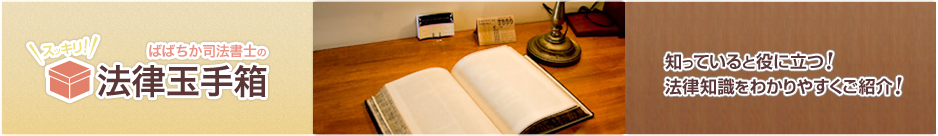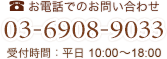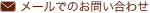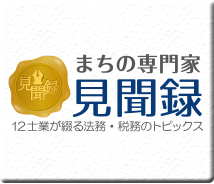自分が意識不明の重体になったとき、延命措置を拒否する方法はある?
2012.11.25 更新
「尊厳死」とはケガや病気で、不治の病で死期が近づいているときに、自分の意思で人間としての尊厳を保ちながら死を迎えるというものです。
過剰ともいえる延命措置を回避する尊厳死
現代の延命医療技術のもとでは、もはや呼吸器しか動いていないという状態を何年も続けるような過剰ともいえる延命措置が施されることがあります。
尊厳死では、そのような状態に自分が置かれることを回避し、延命措置を中止することができます。
「自身の力で呼吸できない人に対して人工呼吸器を装着しない」
「装着している呼吸器のスイッチを切る」
などです。
元気なうちに書面に残しておく「尊厳死宣言公正証書」
この意思表示を、元気なうちに書面に残しておくことができます。
リビングウィルと呼ばれ、具体的には「尊厳死宣言公正証書」として意思表明します。
ただし、尊厳死が注目されているとはいえ、その言葉自体、法律用語ではありませんし、社会的認知を得ているとまではいえない段階であるのが実情です。
必ず意志が実現されるとは限らない
医師の立場としては、回復の可能性が少しでもあるのに治療をやめてしまうことが倫理に反すること、現に生命を保っている患者に対して死に直結する行為が殺人罪に問われるおそれがあることなどから、尊厳死宣言公正証書を残したからといって、必ず意志が実現されるとも限りません。
そこで、尊厳死の意思表示をするときは、以下のことに気を付ける必要があります。
尊厳死の意思表示で気を付けること
◆あらかじめ、家族の了承を得ておく。
周囲の理解を得ずにリビングウィルを作成しても、いざというとき、少しでも長く生きてほしいと願う家族や周囲が困惑すると、せっかくの意向が正しく実現されかねます。
◆医師とよく話し合いをする。
どのような治療を施されることになるのか、その治療の危険性などをよく理解しておく必要があります。
現在、尊厳死の普及を目的とする日本尊厳死協会のアンケート結果によると、「尊厳死公正証書」を示した場合における、医師の尊厳死許容率は9割超だということです。